今週、スイスの新聞に掲載されたモートンのインタビューから、「5月7日にa-haがまた解散する」という話が飛び出しました。いろいろな国のファンから悲鳴のようなコメントが集中し、そのインタビューに同席しなかったマネージャーからは、英語→ドイツ語→英語で広まったことで何か行き違いがあったのではないかと、否定のコメントが出されました。
ファンからの反応は相当なものだったようで、2日後にはa-ha.comから公式発表が出され、モートン本人に話した内容を確認した上で明確に否定されました。*
*ドイツ語の掲載内容をa-ha-live.comが分かりやすい英語にまとめてくれた投稿

声明文の内容;
4月10日付で発行されたBlickのインタビューが混乱を招いてしまったことを申し訳なく思います。
このインタビューでは、Cast In Steelツアーの最終日、5月7日のベルゲン公演でa-haが終わる、モートンはa-haとしての活動では精神的に満たされなくなった、と思わせるような言葉が、他にも、モートンがファンのサポートや注目をありがたく思っていないようなニュアンスの言葉が引用されていました。
これは正しいものではありませんが、誤解があったことに対する私達のお詫びを受け入れていただければと思います。大部分はモートンの話した内容が全て伝えられなかったことによるものです。
昨日のモートンとの会話の中で、彼はまたアルバムを作る可能性があるかどうかを聞かれていた、と話しました。アルバムを一緒に作るには時間がかかるという作業の性質、プロセスをやり抜くには全員が気持ちをこめて専念する必要がある、という内容に関連した(質問への)答えでした。メンバー3人全員が、共同でのアルバム制作は非常に(難しいがやりがいのある)挑戦的なプロセスだと言っていましたから、これは時間の長さにかかわらず、このバンドを見守ってきた人なら誰にとっても目新しいことではありません。
‘Cast In Steel’は、‘アルバム1枚、ツアー1回’のプロジェクトとして発表されており、彼のコメントは単にこれを確認しただけでした。他のプロジェクトはあり得ないという意味ではなく、現時点では何の計画もないということです。
a-haでは精神的に満たされなくなっている、という内容ですが、モートンが言ったのは “現時点では、世界中で群衆を引き付けるa-haのショーで僕はステージの中央にいる。最初のツアーから30年経った今もまた、大勢の人達の心に僕達の音楽が響いているのを感じている。その一部として精神的に属することなしにこんなことができるとは一瞬も思えない。少なくとも僕には不可能だ。”
“最近は一緒にステージにいられる時間を全面的に楽しんでいて、良い意味で一緒に達成できることをとても誇りに思う”、とモートンは言います。
バンドは‘Cast In Steel’ツアーの半分以上を終え、大勢のファンがメンバーに会ったり、サインをもらったり、一緒に写真を撮ったりしたことをFacebookで共有してくれましたが、どの話からもモートン、マグネ、ポールが親切で思いやりをもって応えていたことが分かります。A-haは間違いなくファンに感謝していますが、今回のインタビューでは、この注目が時には非常に疲れるという様子についてモートンが話した内容だけを、彼がどれほど全てのファンに感謝しているかに全く触れず伝えてしまいました。ファンが悲しく思ったり、感謝されていないと感じたとすれば、これは彼の言いたかったことではありませんし、彼は非常に申し訳なく思っています。
5月3日にはオスロで1回限りの特別な公演(Afterglow)が行われますが、先日マグネがファンからの質問に答えた中で、ファンへのプレゼントとしてこのユニークなコンサート・イベントを企画したと話していました。(録画・DVDリリースも計画されているようです)
a-ha.comでは公演前にインスタレーションのスペシャルツアーとメンバーに会えるミーグリに、ファン10名を招待する計画があることも書き添えていました。詳細はまたa-ha.comで発表するそうですが、現在、メルマガ登録者の中から抽選で Hunting High and Low のサイン入りLPが当たるキャンペーンも行われています。
http://a-ha.com/news/articles/win-signed-hunting-high-low-vinyl/
(既に登録済みの場合は待っているだけでOK)
ノルウェー公演6回のうち、4公演はチケット完売となっていますが、特別公演の5月3日、7日最終日のベルゲンは立ち見のためか、まだ購入可能のようです。
誤解が解けて、ファンも心から楽しめるツアーになりますように!
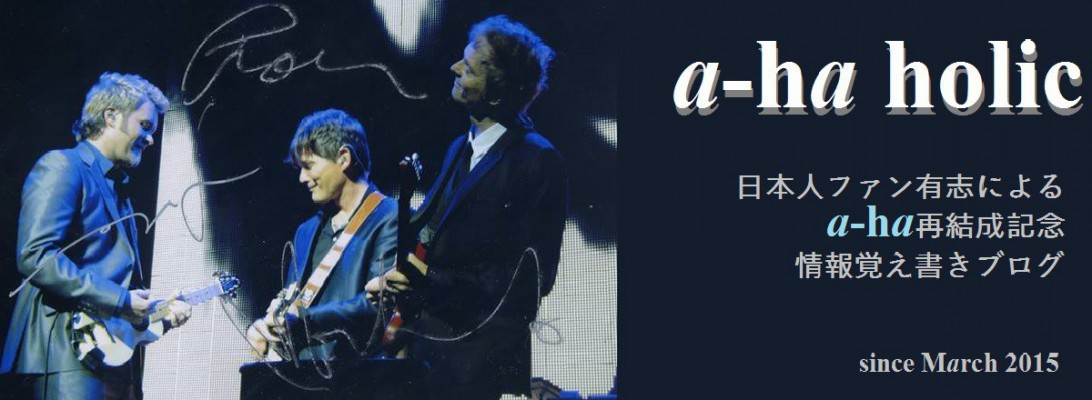
ピンバック: a-ha公式の釈明文の日本語訳がholicに掲載されました、Dagbladetも釈明文を掲載 – With you – With me (Morten Harket.jp)·